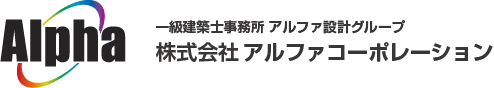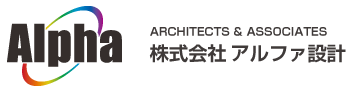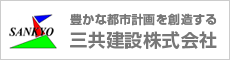度々そう口にしてきましたが、実際のところ、
どうやって説得をするのかが一番肝心な部分ですよね。
けれども、相手も人間なのでそうそう意見が変わるものではありません。
何日も推理を重ねてきた最終日だとなおさらです。
各々自分の軸に基づいて推理を進めて今があるんですから、
その積み重ねた推理に沿った回答を出したくなることでしょう。
ではどんな時に説得が必要かと言われれば、
陣営を問わず自分が黒くなれば自陣営が負けるとき。
及び、自視点で白確定の人が吊られれば負けるとき。
これに尽きるかと思います。
逆を言えば、それ以外の局面においては必須事項ではないと思っています。
負けるかどうかの局面に至るまでに必要なのは、
相手が納得のいく発言を重ねていくこと。
どうやって相手を納得させていくのかと言えば、
それはズバリ「質疑応答」なのです。
人狼ゲームでは基本的に、探りを入れる場合は「質問」という形を取ります。
何も質問せずに相手の黒白を判断した場合、
根拠が見えない考察(=塗り疑惑)ということでやや黒っぽく見られます。
丁寧な質疑応答こそ、説得への近道なのです。
そもそもなぜ質問をするのかと言えば、
- ①相手の言動に違和感を持っている。又は疑っている。
- ②自分の推理を確信したいので相手の思考を探っている。
- ③自分の白アピ、および相手の黒塗り
大体このあたりかなと思います。
上二つは分かるけど最後はどうなのよ、って感じですかね。
でも、人狼ゲームでは、一対一のやり取りでも村の皆に見られるので、
あらゆる発言が要素として拾われていきます。
細やかな思考開示と合わせた質疑応答で、
「自分は村人としてこんな風に勝とうとしています」という、
思考方法や勝ち筋、疑い先の妥当性を“村中に納得”してもらうことこそ、
質疑応答の真の目的なのです。
その際に有効な文章の組立て方が【三角ロジック】
現実社会でもよく使われる方法で、
「データ(事実)」+「論拠」→「結論」で主張を伝えます。
データ:Aはこう発言した
論拠 :今までのAの発言(具体例付で)に沿わない
結論 :回答を受けて自分はこう考える(主張)
例を出すとこんな感じ。
論拠が弱いと質問自体のこじつけ感が強くなります。
最終的な結論で黒いと思うのか白いと思うのかよりも、
そう結論付ける思考過程の方が注視される部分なので、
なんでその質問が自分の推理に必要だったのかは、
過去の発言を根拠に辻褄合わせをしておきましょう。
(なお、ロッカーの場合は急に流暢な論拠が入るとかえって
仲間の存在を疑われることもあるので、
実はここら辺もプレイスタイルによりけりです!笑)
ちなみに論拠の深堀はツッコミ待ちが吉。
または最終日とかに後出しした方がくどくならずにオススメです。
なぜならそれは防御感につながってしまうから。
防御感についてはまた後日お話したいと思います。